貴族の灯りで源氏物語の世界を照らす!れきし発掘隊(平安バージョン)




- 販売価格
-
1組(子ども1人+大人1人) :¥13,200(税込)
お土産の書写作品と、灯りに必要な材料(搾油など)代を含みます。人数追加は、6,600円/名でご参加可能です。れきし発掘隊一覧はこちら
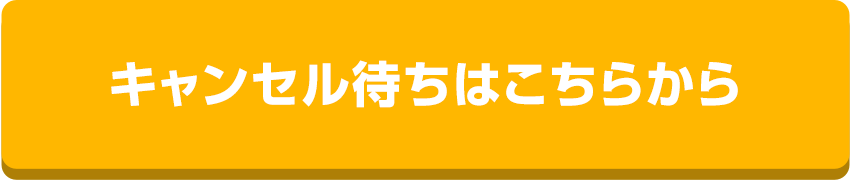
- 開催日時&残席状況
(◯:あきあり △:あとわずか ✕:満席) 09月14日(日) 09:00-12:00 (☓)
09月14日(日) 13:30-16:30 (☓)
- 開催場所
伊弉諾神社(埼玉県熊谷市)東北自動車道「羽生IC」から約35分、関越自動車道「東松山IC」から約45分、現地に無料駐車場ありJR熊谷駅よりバス15分、最寄りバス停より徒歩1分
大反響となっている「日本の歴史」を五感を使って遊んで学ぶ「れきし発掘隊」に、平安貴族の文学と夜をテーマにした新作が登場です。
日本の歴史の中でも、特にユニークな貴族の時代である「平安」が今回のテーマです。約390年もの間、平和と安定がおおむね続き、国風文化で「日本」が確立した時代でもあります。
体験の中では、この時代の中心である「貴族の生活と文化」に焦点を当てます。「貴族の生活」としては、平安時代の夜を照らした「灯り」づくり体験を行います。
灯りが完成したら、「貴族の文化」の象徴でもある、「源氏物語」の夜の場面を再現します。お部屋を暗くして、灯りをつけて、プロジェクターに投影した満月のもとで、貴族が使ったお香や和楽器の音などに包まれて平安時代を体感します。
最後は、平安の夜の雰囲気の中で、筆ペンを使った書写を行います。自分で作り出した灯りのもとで、貴族も虜になった仮名文字のおもしろさを体験します。
体験の企画・運営をおこなう三菅洋輔(みっちゃん)先生は、小中学校で活躍した元「社会科教諭」で、理想の学びの形を目指して独立されました。
日本史の中でも特にユニークな貴族が主人公だった平安時代を、源氏物語の夜の場面の再現で体感する「れきし発掘隊」に、ぜひ親子でご参加ください。
★★★
奈良時代の仏像作りはこちら
戦国時代の甲冑作りはこちら
江戸時代の浮世絵作りはこちら
幕末時代の写真機作りはこちら

平安時代の「灯り」を作って、貴族の夜の灯りを体感する平安体験!
ギフテの大人気シリーズである「れきし発掘調査隊」では、日本の歴史を、自分の五感で感じながら、遊ぶように学び、興味や好奇心を深掘りすることを目指しています。
今回のテーマ「平安時代」は、日本の歴史上類を見ない400年近く続いた貴族と文化の時代です。奈良時代までの王族・豪族の時代から、鎌倉時代以降の武士の時代の転換点になった、中世の入り口に位置します。
 今回はそんな「貴族の生活と文化」にフォーカスし、生活が豊かになってきたことで、夜を照らすことができるようになった「灯り」作りに取り組みます。
貴族の生活にはいくつもの特徴がありますが、夜を有効活用できるようになったことで、社交的な世界が広がったことは、文化面でも大きな影響を及ぼしました。
今回はそんな「貴族の生活と文化」にフォーカスし、生活が豊かになってきたことで、夜を照らすことができるようになった「灯り」作りに取り組みます。
貴族の生活にはいくつもの特徴がありますが、夜を有効活用できるようになったことで、社交的な世界が広がったことは、文化面でも大きな影響を及ぼしました。
 体験当日は、平安の夜を照らした「灯り」を、当時の仕組みをベースに手作りするところからスタートします。
平安時代の「灯り」を、燃料となる植物性の油を搾り、和紙を使って再現します。当時に近い「灯り」を通して、貴族の生活をイメージしてみましょう。
体験当日は、平安の夜を照らした「灯り」を、当時の仕組みをベースに手作りするところからスタートします。
平安時代の「灯り」を、燃料となる植物性の油を搾り、和紙を使って再現します。当時に近い「灯り」を通して、貴族の生活をイメージしてみましょう。

投影した満月の下で、お香や和楽器の音に囲まれて源氏物語の場面を再現!
「貴族の生活」を体感できる灯りが完成したら、次は「貴族の文化」にふれる再現体験をしていきます。
国風文化として、日本独自の文化が花開いた平安時代の象徴といえば、なんといっても「文学」です。とりわけ世界最古の長編小説である「源氏物語」はこの時代を代表する作品です。
 当日は、源氏物語の夜の場面の再現として、室内を暗くして、プロジェクターに満月や天の川を投影します。
平安の夜の舞台が整ったら、自分たちで用意した「灯り」をともして、源氏物語の場面をみんなで迎えましょう。
当日は、源氏物語の夜の場面の再現として、室内を暗くして、プロジェクターに満月や天の川を投影します。
平安の夜の舞台が整ったら、自分たちで用意した「灯り」をともして、源氏物語の場面をみんなで迎えましょう。
 さらに、視覚以外にも平安文化を体感できるよう、当時に近い香りのお香を焚き、和楽器の音楽も流して、五感で源氏物語の世界を感じていきます。
源氏物語の夜の場面の再現を通して、貴族の生活と文化に思いを馳せて「平安の風」を感じる時間を過ごしてもらえればと思います。
さらに、視覚以外にも平安文化を体感できるよう、当時に近い香りのお香を焚き、和楽器の音楽も流して、五感で源氏物語の世界を感じていきます。
源氏物語の夜の場面の再現を通して、貴族の生活と文化に思いを馳せて「平安の風」を感じる時間を過ごしてもらえればと思います。
 最後は、平安の夜の雰囲気の中で、筆ペンを使った書写を行います。自分で作り出した灯りのもとで、貴族も虜になった仮名文字のおもしろさを体験します。
最後は、平安の夜の雰囲気の中で、筆ペンを使った書写を行います。自分で作り出した灯りのもとで、貴族も虜になった仮名文字のおもしろさを体験します。

社会科教諭だった三菅先生が、学校では叶わなかった理想の歴史授業を体感!
今回の体験の企画・運営は、小中学校で活躍した元「社会科教諭」の三菅洋輔(みっちゃん)先生と、公立幼稚園・小学校で教諭をされていた三菅香澄(かっちゃん)先生のご夫婦です。
お二人は、学校の教育現場だけでは実現が難しかった、探究と体験から学ぶ場をつくる活動をおこなう団体「種をまく」を立ち上げました。
「種をまく」とギフテの新しい取り組みである「れきし発掘調査隊」では、日本の歴史を、自分の五感で感じながら、遊ぶように学び、興味や好奇心を深掘りすることを目指しています。
▼ご夫婦で公教育の現場で活躍されていた、みっちゃん先生(左)とかっちゃん先生(右)
 体験の舞台は、埼玉県熊谷市にある伊弉諾(いざなぎ)神社と、境内の集会所です。
自家用車の場合は、会場に無料駐車場を用意しており、東北自動車道羽生ICから約35分、関越自動車道東松山ICから約45分です。公共交通機関の場合は、都心からアクセスの良いJR熊谷駅からバスで15分、最寄りのバス停より徒歩1分です。
体験の際は、神社のお手洗いをお借りできるので、小さなお子様連れでも安心してご参加いただけます。また、雨天の場合でも集会所があるので、柔軟なフォローが可能です。
▼集合場所でもある伊弉諾神社
体験の舞台は、埼玉県熊谷市にある伊弉諾(いざなぎ)神社と、境内の集会所です。
自家用車の場合は、会場に無料駐車場を用意しており、東北自動車道羽生ICから約35分、関越自動車道東松山ICから約45分です。公共交通機関の場合は、都心からアクセスの良いJR熊谷駅からバスで15分、最寄りのバス停より徒歩1分です。
体験の際は、神社のお手洗いをお借りできるので、小さなお子様連れでも安心してご参加いただけます。また、雨天の場合でも集会所があるので、柔軟なフォローが可能です。
▼集合場所でもある伊弉諾神社
 日本史の中でも特にユニークな貴族が主人公だった平安時代を、源氏物語の夜の場面の再現で体感する「れきし発掘隊」に、ぜひ親子でご参加ください。
日本史の中でも特にユニークな貴族が主人公だった平安時代を、源氏物語の夜の場面の再現で体感する「れきし発掘隊」に、ぜひ親子でご参加ください。
- 先生プロフィール
-

◆三菅洋輔(みっちゃん)先生(写真) 埼玉県熊谷市出身。元公立小中学校教員。社会や道徳、総合的な学習の時間、特別支援を研究していた。 ◆三菅香澄(かっちゃん)先生 埼玉県熊谷市出身。元公立幼稚園小学校教員。中高音楽の教員免許所持。吹奏楽部の指導経験あり。 現在は、「種をまく」で探究と体験から学ぶ場をつくる活動をしている。
- 体験者の声
-
★初開催のため、すでに開催実績のあるれきし発掘隊の別バージョンのお声です ・インストラクターのお二人が、子供の気持ちを盛り立てて積極的に取り組めるように声掛けをしてくださった。 ・如何に作るのが難しいかがわかる。歴史は今と繋がっているというのがわかる。 ・弥生時代の人と同じように火おこし、型作りから始まり、綺麗な青銅器を作るのがいかに難しいか、なぜ職業集団ができたのか、物作りの楽しみだけでなく体験を通して「なぜ」を考え、歴史を学べることができました。
- 対象年齢
5歳以上2人目以降の4歳以下のお子様は無料です(体験・お土産の提供はありません)
- 学べる要素
考えるチカラ
- 開催日時&残席状況
(◯:あきあり △:あとわずか ✕:満席) 09月14日(日) 09:00-12:00 (☓)
09月14日(日) 13:30-16:30 (☓)
- 開催場所
伊弉諾神社(埼玉県熊谷市)東北自動車道「羽生IC」から約35分、関越自動車道「東松山IC」から約45分、現地に無料駐車場ありJR熊谷駅よりバス15分、最寄りバス停より徒歩1分
- 集合場所
伊弉諾神社地図はこちら
- 定員
各回20名程度(最小催行8名)
- 提供元
- 持ち物/服装
-
・汚れてもよい服装・靴 ・筆ペン(親子で2本推奨だが1本でもOK) ・タオルや暑さ対策グッズ(推奨) ・飲み物(熱中症対策に多めにお持ちください) ・参加者の健康保険証
- 当日のスケジュール
-
★午前の部の場合 8:45~9:00 受付 9:00~9:30 オリエンテーション 9:30~10:30 灯りづくり体験 10:30~11:00 源氏物語の夜の場面の再現体験 11:00〜11:40 平安かな文字書写体験 11:40~12:00 クロージング
- 備考
-
・室内での体験となるため、雨天でも基本的に開催します。警報を伴うような悪天候の場合は、前日夕方までに中止のご連絡を差し上げます。




