伝統的な絵の具を手作りして、風流な浮世絵を刷り上げる!れきし発掘隊(江戸バージョン)




- 販売価格
-
1組(子ども1人+大人1人) :¥14,300(税込)
体験料金+刷り上げた浮世絵作品(はがきサイズ3枚)のお土産つき。人数追加は、大人・子どもとも7,150円/名でご参加可能です。れきし発掘隊一覧はこちら
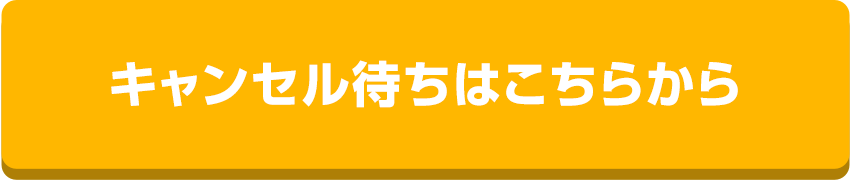
- 開催日時&残席状況
(◯:あきあり △:あとわずか ✕:満席)
- 開催場所
※8/10は「熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ」に変更。伊弉諾神社の集会所とその周辺のフィールド(埼玉県熊谷市)東北自動車道「羽生IC」から約35分、関越自動車道「東松山IC」から約45分、現地に無料駐車場ありJR熊谷駅よりバス15分、最寄りバス停より徒歩1分
大反響となっている「日本の歴史」を五感を使って遊んで学ぶ「れきし発掘隊」、縄文→弥生→古墳と来て、次は一気に時代が飛んで「江戸時代」です。
江戸時代は、戦国までの武士の争いが終わり、時代の主役が一部の権力者から民衆に移り、町人文化が花開いた時代です。
この江戸時代の町人文化の象徴が、日本画の代名詞とも言われる「浮世絵」です。今回の体験では、伝統的な絵の具作りからはじめて、版画を彫って、色を重ねて刷り上げて、浮世絵作品を完成させます。
体験の中では、葛飾北斎の「凱風快晴」「あやめにきりぎりす」と、歌川国政「市川鰕蔵 暫」の3点をモチーフに、はがきサイズの浮世絵を制作してお土産にお持ち帰りいただく予定です。
体験の企画・運営をおこなう三菅洋輔(みっちゃん)先生は、小中学校で活躍した元「社会科教諭」で、理想の学びの形を目指して独立されました。
伝統的な絵の具作りから、版画を彫って、色を重ねて刷り上げる、本格的な浮世絵作り体験を通して、日本の歴史への興味と好奇心を掘り出す「れきし発掘隊」に、ぜひ親子でご参加ください。
★★★
奈良時代の仏像作りはこちら
戦国時代の甲冑作り&合戦体験はこちら

江戸時代と同じ材料・方法で、自然から伝統的な絵の具を作り出す!
みっちゃん先生とギフテの新しい取り組みである「れきし発掘調査隊」では、日本の歴史を、自分の五感で感じながら、遊ぶように学び、興味や好奇心を深掘りすることを目指しています。
今回のテーマ「江戸時代」は、戦国の時代が終わり、時代の中心が一部の権力者から大衆に移って町人文化が花開いた時期になります。
▼260年続く江戸時代は中世と近代をつなぐ重要な時代です
 今回はそんな江戸時代を体感するために、この時代の象徴の一つである「浮世絵」にフォーカスし、絵の具作りから版画の刷り上げまでを体験します。
体験の中では、江戸時代の絵の具作りのプロセスを再現すべく、当時、色を採取していた樹皮を探すところからスタートします。
今回はそんな江戸時代を体感するために、この時代の象徴の一つである「浮世絵」にフォーカスし、絵の具作りから版画の刷り上げまでを体験します。
体験の中では、江戸時代の絵の具作りのプロセスを再現すべく、当時、色を採取していた樹皮を探すところからスタートします。
 樹皮が見つかったら、煮詰めて「にかわ」を混ぜ、江戸時代の絵の具が完成します。
色々な樹皮を集めて、カラフルな浮世絵の世界を再現する絵の具をそろえましょう。
できるだけ伝統的な自然の染料を探しますが、浮世絵作りに不足する場合は、先生があらかじめ用意した染料や絵の具を使いますので、ご了承ください。
樹皮が見つかったら、煮詰めて「にかわ」を混ぜ、江戸時代の絵の具が完成します。
色々な樹皮を集めて、カラフルな浮世絵の世界を再現する絵の具をそろえましょう。
できるだけ伝統的な自然の染料を探しますが、浮世絵作りに不足する場合は、先生があらかじめ用意した染料や絵の具を使いますので、ご了承ください。
 浮世絵は、世界的に有名な日本の伝統文化ですが、印刷技術の発展に伴い、その技術や技法を継承する職人は減少しています。
一方で、私たちの身の回りには、浮世絵で使われた絵の具の原料がたくさんあります。江戸時代の絵の具作り体験を通して、先人の知恵と自然の恵みを体感する機会を目指します。
浮世絵は、世界的に有名な日本の伝統文化ですが、印刷技術の発展に伴い、その技術や技法を継承する職人は減少しています。
一方で、私たちの身の回りには、浮世絵で使われた絵の具の原料がたくさんあります。江戸時代の絵の具作り体験を通して、先人の知恵と自然の恵みを体感する機会を目指します。

有名な作品をモチーフに、版画を掘って、自家製絵の具で三色に刷り上げる浮世絵作り!
江戸時代の絵の具が完成したら、いよいよ浮世絵を作り上げる体験を行います。
浮世絵は、出版物としての取りまとめを行う「版元(はんもと)」、絵を描く「絵師(えし)」、版画を作る「彫師(ほりし)」、そして印刷を担当する「摺師(すりし)」の4種類の職人によって成立していました。
今回の体験では、浮世絵の原画として特に有名な葛飾北斎の「凱風快晴」「あやめにきりぎりす」と、歌川国政「市川鰕蔵 暫」の3点をモチーフに、複数の色を重ねて刷り上げる体験をします。
▼写真右上の赤い富士山が葛飾北斎の「凱風快晴」です
 版画については、3つの作品を用意した板にカーボン紙で複写して、自分の手で彫刻刀で刻む「彫師体験」を行います。
有名な作品をモチーフにしつつ、親子でオリジナルの浮世絵作品にすることも可能です。小さなお子様は保護者の方にフォローしていただければと思います。
版画については、3つの作品を用意した板にカーボン紙で複写して、自分の手で彫刻刀で刻む「彫師体験」を行います。
有名な作品をモチーフにしつつ、親子でオリジナルの浮世絵作品にすることも可能です。小さなお子様は保護者の方にフォローしていただければと思います。
 オリジナルの浮世絵版画が完成したら、いよいよ「摺師体験」の時間です。
自分たちで作った自家製の絵の具を使って、はがきサイズの和紙の上に、それぞれの浮世絵を三色に分けて刷っていきます。和紙の上に色が重なっていく様子を、江戸時代と同じ画材で体感してもらえます。
最後に、消しゴムを加工して作るオリジナルの落款(らっかん)を押して、自分だけの浮世絵作品が完成です。
刷り上がった3種類の浮世絵作品は、もちろんお土産にお持ち帰りいただけます。
オリジナルの浮世絵版画が完成したら、いよいよ「摺師体験」の時間です。
自分たちで作った自家製の絵の具を使って、はがきサイズの和紙の上に、それぞれの浮世絵を三色に分けて刷っていきます。和紙の上に色が重なっていく様子を、江戸時代と同じ画材で体感してもらえます。
最後に、消しゴムを加工して作るオリジナルの落款(らっかん)を押して、自分だけの浮世絵作品が完成です。
刷り上がった3種類の浮世絵作品は、もちろんお土産にお持ち帰りいただけます。


社会科教諭だった三菅先生が、学校では叶わなかった理想の歴史授業を体現!
今回の体験の企画・運営は、小中学校で活躍した元「社会科教諭」の三菅洋輔(みっちゃん)先生と、公立幼稚園・小学校で教諭をされていた三菅香澄(かっちゃん)先生のご夫婦です。
お二人は、学校の教育現場だけでは実現が難しかった、探究と体験から学ぶ場をつくる活動をおこなう団体「種をまく」を立ち上げました。
「種をまく」とギフテの新しい取り組みである「れきし発掘調査隊」では、日本の歴史を、自分の五感で感じながら、遊ぶように学び、興味や好奇心を深掘りすることを目指しています。
▼ご夫婦で公教育の現場で活躍されていた、みっちゃん先生(左)とかっちゃん先生(右)
 体験の舞台は、埼玉県熊谷市にある伊弉諾(いざなぎ)神社とその近くの畑です。古事記で伝えられる日本列島誕生の神話に出てくるイザナギ神と同じ名前の神社が体験の舞台というのも、不思議なご縁を感じます。
▼集合場所でもある伊弉諾神社
体験の舞台は、埼玉県熊谷市にある伊弉諾(いざなぎ)神社とその近くの畑です。古事記で伝えられる日本列島誕生の神話に出てくるイザナギ神と同じ名前の神社が体験の舞台というのも、不思議なご縁を感じます。
▼集合場所でもある伊弉諾神社
 自家用車の場合は、会場に無料駐車場を用意しており、東北自動車道羽生ICから約35分、関越自動車道東松山ICから約45分です。公共交通機関の場合は、都心からアクセスの良いJR熊谷駅からバスで15分、最寄りのバス停より徒歩1分です。
体験の際は、神社の集会所とお手洗いをお借りできるので、小さなお子様連れでも安心してご参加いただけます。また、雨天の場合でも集会所があるので、柔軟なフォローが可能です。
▼神社の集会所をお借りして青銅器作り体験やお話しをします
自家用車の場合は、会場に無料駐車場を用意しており、東北自動車道羽生ICから約35分、関越自動車道東松山ICから約45分です。公共交通機関の場合は、都心からアクセスの良いJR熊谷駅からバスで15分、最寄りのバス停より徒歩1分です。
体験の際は、神社の集会所とお手洗いをお借りできるので、小さなお子様連れでも安心してご参加いただけます。また、雨天の場合でも集会所があるので、柔軟なフォローが可能です。
▼神社の集会所をお借りして青銅器作り体験やお話しをします

伝統的な絵の具作りから、版画の刷り上げまで行う本格的な浮世絵作り体験を通して、日本の歴史への興味と好奇心を掘り出す「れきし発掘隊」に、ぜひ親子でご参加ください。
- 先生プロフィール
-

◆三菅洋輔(みっちゃん)先生(写真) 埼玉県熊谷市出身。元公立小中学校教員。社会や道徳、総合的な学習の時間、特別支援を研究していた。 ◆三菅香澄(かっちゃん)先生 埼玉県熊谷市出身。元公立幼稚園小学校教員。中高音楽の教員免許所持。吹奏楽部の指導経験あり。 現在は、「種をまく」で探究と体験から学ぶ場をつくる活動をしている。
- 体験者の声
-
★初開催のため、すでに開催実績のある同じ先生の縄文バージョンのお声です ・インストラクターのお二人が、子供の気持ちを盛り立てて積極的に取り組めるように声掛けをしてくださった。
- 対象年齢
5歳以上2人目以降の4歳以下のお子様は無料です(体験・お土産の提供はありません)
- 学べる要素
考えるチカラ
- 開催日時&残席状況
(◯:あきあり △:あとわずか ✕:満席)
- 開催場所
※8/10は「熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ」に変更。伊弉諾神社の集会所とその周辺のフィールド(埼玉県熊谷市)東北自動車道「羽生IC」から約35分、関越自動車道「東松山IC」から約45分、現地に無料駐車場ありJR熊谷駅よりバス15分、最寄りバス停より徒歩1分
- 集合場所
現地集合※8/10は「熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ」に変更。地図はこちら
- 定員
各回20名程度(最小催行8名)
- 提供元
- 持ち物/服装
-
【持ち物】飲み物、軍手、参加者の健康保険証 【服装】汚れてもよい服装・靴
- 当日のスケジュール
-
★午前の部の場合 8:45~9:00 受付 9:00 集合・ミーティング 9:10 フィールドワークをして樹木を採取 9:40 樹木を細かく砕く 10:00 鍋で煮詰める・消しゴム落款づくり・版木づくり 10:30 にかわを加え絵の具完成 10:50 浮世絵を刷る 11:45 最後に落款を押して完成! 12:00 解散
- 備考
-
・集会所も使えるため雨天開催ですが、警報が出るような悪天候の場合は中止もしくは延期のご連絡を、前日夕方までに差し上げます。・当日は高速等で渋滞が予測されますので、お車の場合はお時間に余裕をもってお越しください。




