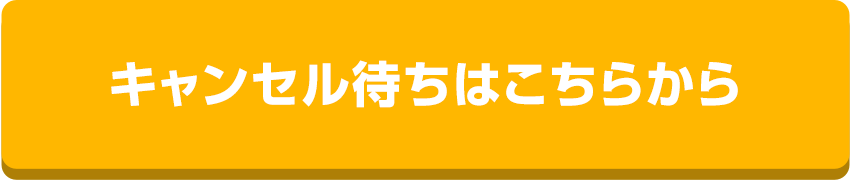最先端のエネルギー技術「超小集電」に迫る!サイエンスリサーチャー体験




- 開催日時&残席状況
(◯:あきあり △:あとわずか ✕:満席)
- 開催場所
トライポッド本社内にある研究施設都営地下鉄「九段下駅」から徒歩5分お車の場合、近隣のコインパーキングをご利用ください
ギフテのオリジナリティ溢れる学び体験に、また新しいラインナップが登場します。なんと、土や水、野菜などあらゆる自然物から微小な電力を集めて使う最先端の自然エネルギー技術にふれる科学体験です。
テレビなどのメディアでご覧になったことがあるかもしれませんが、この「超小集電」と言われる技術は、東京大学大学院で特任教授も務められた中川聰教授が、微生物燃料電池の研究の過程で発見したものです。
土や水だけでなく、スイカやパンなど、あらゆる自然物に2つの異なる電極を刺すことで、非常に小さな電力を取り出すことができます。この非常に小さな電力の存在に着眼し、活用する術を見出したのが「超小集電」です。
電線がなく、電力が供給されていない地球上のどのような地域でも灯りを点けることができるため、将来的に人類に貢献する画期的な発明になる可能性があります。
今回はギフテ!の活動に賛同してくれた中川教授が、超小集電の研究施設(ラボ)を舞台に、自ら先生を務めて、この最先端の技術の説明と実験体験をしてくれることになりました。
地球を救うかもしれない最先端の超小集電技術にふれ、電気やエネルギーについて考えるきっかけを作る、超小集電のサイエンスリサーチャー体験に、ぜひ親子でお越しください。

スイカやパン、土からも集電できる!驚きの最新技術「超小集電」を学ぶスペシャル企画!
今回の体験で取り扱う「超小集電」とは、「あらゆる自然物を媒体として、集電材(電極)を介して、微小な電気を収集する技術」とのことです。
すごくシンプルに言うと、「自然物にプラスとマイナスの電極を刺すことで、乾電池のように電気を取り出せる」ということになります。驚くことに、この自然物とは、土でも、水でも、野菜でもなんでも良いのです。
通常の乾電池であれば、電池の中に電解物質(マンガンとかニッケルとか電池の前につくものが多い)が入っていて、そこに電気回路とつなぐと、電解物質が化学反応を起こして発電します。
しかし、この「超小集電」では、電池の中に入れている効果の高い電解質を使わず、自然物から直接わずかな電力を取り出して、それをたくさん集めて使える電気にする、という考え方で設計されています。
▼実際にパンに電極を刺してLEDライトが光っている様子
 ただ少し変わった発電方法でLEDライトが光るだけなら、それほど驚かれないかもしれませんが、この「超小集電」のすごいところは、電極さえあれば、乾電池や蓄電池はもとより電線やコンセントがない砂漠や荒野でも電気製品が使える、ということです。
ユニセフの発表によると、世界にはまだ電気を全く使えない人が6億5000万人いるとされ、開発が遅れている地域にとっては、この研究はまさに希望の光になる可能性があります。
▼超小集電の装置に「ただの土」を挟んで集電している様子
ただ少し変わった発電方法でLEDライトが光るだけなら、それほど驚かれないかもしれませんが、この「超小集電」のすごいところは、電極さえあれば、乾電池や蓄電池はもとより電線やコンセントがない砂漠や荒野でも電気製品が使える、ということです。
ユニセフの発表によると、世界にはまだ電気を全く使えない人が6億5000万人いるとされ、開発が遅れている地域にとっては、この研究はまさに希望の光になる可能性があります。
▼超小集電の装置に「ただの土」を挟んで集電している様子
 開発が遅れている地域だけでなく、私たちの暮らしにおいても、停電時の備えはもちろん、カーボンを排出しない点や化石燃料に頼らない点で、新たな再生可能エネルギーとしても大きな可能性を秘めています。
もちろん、「超小」の名の通り、自然物から取り出せる電力はわずかのため、「集電」する技術があっても、現時点ではLEDライトを灯すことが中心です。
しかし集電の規模を大きくすれば、通常の家電製品を動かすこともでき、これから更に研究・開発が進むことで、より大きなインパクトを発揮できるようになることが期待されています。
開発が遅れている地域だけでなく、私たちの暮らしにおいても、停電時の備えはもちろん、カーボンを排出しない点や化石燃料に頼らない点で、新たな再生可能エネルギーとしても大きな可能性を秘めています。
もちろん、「超小」の名の通り、自然物から取り出せる電力はわずかのため、「集電」する技術があっても、現時点ではLEDライトを灯すことが中心です。
しかし集電の規模を大きくすれば、通常の家電製品を動かすこともでき、これから更に研究・開発が進むことで、より大きなインパクトを発揮できるようになることが期待されています。
 この体験ではそんな未来のエネルギー技術である「超小集電」の仕組みを、中川教授の説明やラボの見学、様々な実験体験を通して、この技術を直接体感してもらうのが目的です。
この体験ではそんな未来のエネルギー技術である「超小集電」の仕組みを、中川教授の説明やラボの見学、様々な実験体験を通して、この技術を直接体感してもらうのが目的です。
 【ご参考】超小集電を特集したBSフジの番組
【ご参考】超小集電を特集したBSフジの番組
千代田区九段下にある超小集電の研究施設が科学体験の舞台!
体験の舞台は、東京都千代田区九段下にある、超小集電の研究施設(ラボ)になります。中川教授が代表を務めている、トライポッド・デザイン株式会社の本社内になります。
▼トライポッド・デザイン株式会社の入り口
 ラボの中には、超小集電の仕組みを説明したパネルや、実際に様々なもので発電している様子が展示されています。体験の中では、レッスンと合わせて、ラボツアーも実施します。
ラボの中には、超小集電の仕組みを説明したパネルや、実際に様々なもので発電している様子が展示されています。体験の中では、レッスンと合わせて、ラボツアーも実施します。
 ラボツアーの中では、展示物を見ながら中川教授や、サポートの先生方に質問をすることもでき、お子さんの理解も深まることが期待できます。
ラボツアーの中では、展示物を見ながら中川教授や、サポートの先生方に質問をすることもでき、お子さんの理解も深まることが期待できます。
 当日はレッスンとラボ見学と合わせ、実際に発電している様子をデモンストレーションしてくれるので、記事だけでは伝わらない超小集電の力を体感できます。
当日はレッスンとラボ見学と合わせ、実際に発電している様子をデモンストレーションしてくれるので、記事だけでは伝わらない超小集電の力を体感できます。

「超小集電」の発見者である、中川教授自ら解説&一緒に実験体験!
今回の体験の先生は、自然物に宿るわずかな電力に着眼し、それを取り出して利用する超小集電の技術を確立した、中川 聰(なかがわ さとし)教授自らが担当してくれる予定です。
中川教授は、2018年までは東京大学大学院の工学系研究科で特任教授を務められ、2020年からは名古屋大学の医学部で客員教授を務められています。
今回は、未来を生きる子ども達にエネルギーの新しい可能性を伝えたいという想いで、ギフテ!との特別なコラボ企画が実現しました。
▼超小集電の発見者である中川教授
 体験の中ではラボに併設された広いワークショップスペースを舞台に、レッスンだけでなく、実際に五感を使って超小集電にふれる実験体験も行います。
▼子ども達と実験体験を行う中川教授(当日は室内で行います)
体験の中ではラボに併設された広いワークショップスペースを舞台に、レッスンだけでなく、実際に五感を使って超小集電にふれる実験体験も行います。
▼子ども達と実験体験を行う中川教授(当日は室内で行います)


地球を救うかもしれない最先端の超小集電技術にふれ、電気やエネルギーについて考えるきっかけを作る、超小集電のサイエンスリサーチャー体験に、ぜひ親子でお越しください。
- 先生プロフィール
-

中川 聰(なかがわ さとし)先生 プロダクトデザイナー/デザイン・エンジニア/デザインコンサルタント トライポッド・デザイン株式会社CEO 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学医学部 客員教授(2020年〜) 元東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻特任教授(〜2018年) 1987年にプロダクトデザイナーとしてトライポッド・デザインを設立。様々な使い手のデザインにおける使いにくさに着目したリード・ユーザー理論による独自のユニバーサルデザインテクノロジーや評価法を発表し、広く国内外の企業の製品企画や公共空間のユニバーサルデザインの開発と普及に携わる。2005年にはユーザーの行動心理に着目した感性デザインの理論体系である「期待学 / EXPECTOLOGY」理論を発表し、製品やサービスにおける様々な使い手の不安や期待心理を研究分析するプロジェクトを開始する。 2010年には人間の五感を支援拡張する目的で開発した新たな人工感覚概念「SUPER SENSING」理論を提唱し、以後人間の感覚や思考の拡張に注目したハードウエアやアプリケーション開発に取り組んでいる。2016年には、次世代の人材育成を目的に掲げた企業共創によるコワーキング研究機構「FUTURE BRAIN LAB」の事業構想を発表し、その開設に向けた準備活動を進めている。2019年にはセンシング技術の開発過程で電気化学の新たな領域発見と称される「超小集電」の理論と技術を見出し、無電環境における電気エネルギー供給を可能にする産業技術の出現として国際的な関心を集めつつある。 ★ご参加人数に応じて、知識と経験のあるラボ関係者がサポートに入ります。
- 対象年齢
小学校4年生から6年生小2,3年生・中学生以上はご希望あれば参加可能小学1年生以下は参加/同伴ともに不可対象年齢外の場合、小4〜6年向けのプログラムであることをご理解の上、ご参加ください
- 学べる要素
考えるチカラ
- 開催日時&残席状況
(◯:あきあり △:あとわずか ✕:満席)
- 開催場所
トライポッド本社内にある研究施設都営地下鉄「九段下駅」から徒歩5分お車の場合、近隣のコインパーキングをご利用ください
- 集合場所
トライポッド・デザイン株式会社(東京都千代田区)地図はこちら
- 定員
12組最小催行:5組
- 提供元
- 持ち物/服装
-
飲料 筆記用具
- 当日のスケジュール
-
★AMの場合 10:00-10:10 ウェルカムライト 10:10-10:20 ラボニュース 10:20-10:30 超小集電の謎と仕組み 10:30-10:45 集電トライアルクイズ 10:45-11:00 休憩 11:00-11:20 小さな電気を活かせる暮らし 11:20-11:40 電気を飛ばそう 未来への実験 11:40-12:00 クロージング
- 備考
-
・室内での体験のため、警報の出るような悪天候でない限りは開催します。・ラボには高額な設備や機械もあるため、見学の際は、保護者様の方でしっかりと安全管理をお願いします。・電気の単元は小学校4年生の理科ではじめて習うため、小学4年生以上のご参加が推奨です。参加者の方のご希望があれば、推奨年齢と学習内容をご理解の上で、小学2,3年生と中学生以上はご参加可能です。小学1年生以下のお子様は、大変申し訳ありませんが、ご参加・ご見学ともできませんのでご了承ください。尚、近隣には科学技術館などもあります。